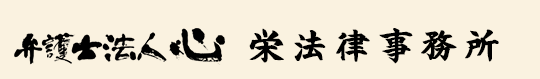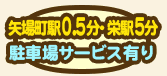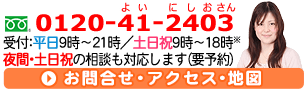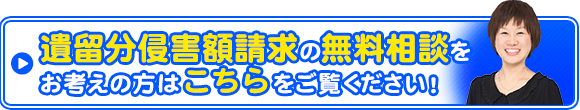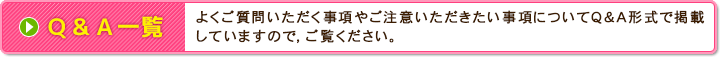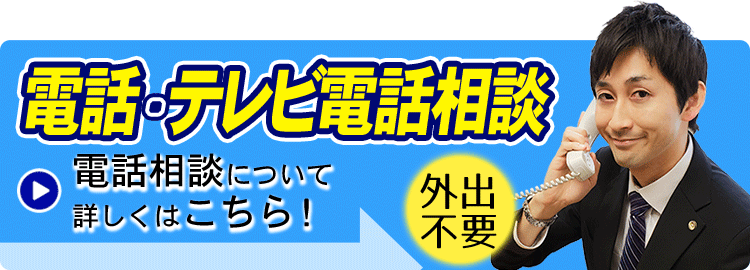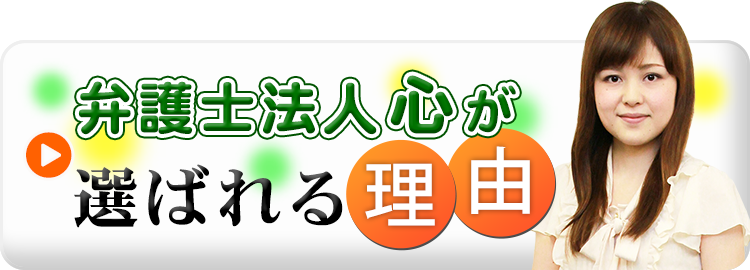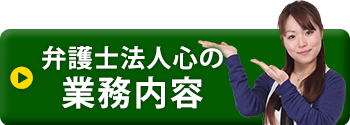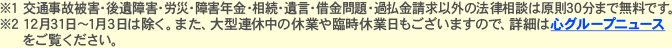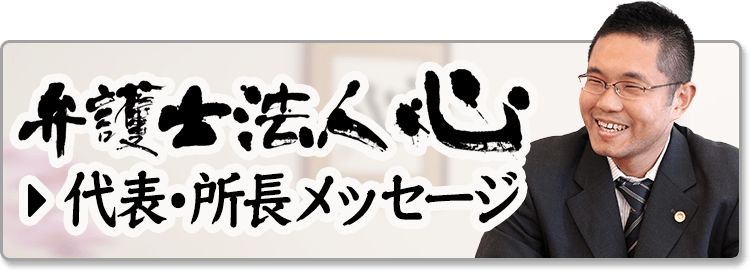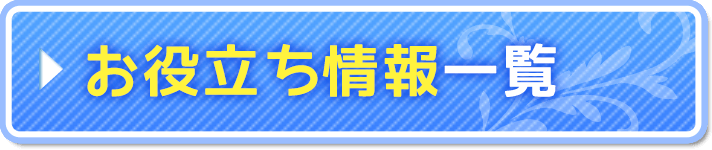遺留分の金銭債権化
1 金銭債権化された理由
遺留分の権利については、平成30年の相続法改正によって、金銭債権化されました。
法改正前は、個別の遺産に対する物権的な権利とされていました。
どのようなことかといいますと、例えば、相続財産に不動産が含まれていた場合には、遺留分の侵害の割合によって、当該不動産に権利者の持分が生じるとされていたということです。
しかし、個別の遺産に対する物権的な権利だと、支障が生じるケースがあります。
例えば、亡くなった方が栄で事業をしていた場合を考えます。
その事業に関する財産が遺産に含まれている場合には、上記のような効果が生じることが事業の遂行の妨げになるおそれがあります。
相続財産の中に栄の不動産が含まれている場合についても考えてみます。
従来であれば、この不動産についても、請求をする側と請求をされる側との共有の状態となります。
しかし、遺留分の請求をするにあたり、双方の間で紛争となったことが容易に想定される中、不動産の共有状態が続くことは望ましくないといえます。
そして、この状態を解消するために、また新たな紛争が続くことが想定されます。
このようなことが考えられるため、遺留分の権利を金銭債権化することによって、遺留分請求による上述したような弊害が生じることがないように法改正がされました。
なお、現在の遺留分についての権利は、相続人の生活保障や遺産形成に貢献した相続人の潜在的持分の確保を制度趣旨とされていると解釈されているところ、金銭債権化することによって、このような制度趣旨が害されることがないだろうということも考慮されました。
2 権利行使の効果と消滅時効
遺留分についての権利を行使する際は、従来も受遺者等に対してその内容を具体的に明示して行わなくとも効果が生じるものとされてきました。
遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年以内にこの権利を行使しなければ、消滅時効によってこの権利が消滅することは、従来と同じであり、この請求においては請求額を明示する必要がないことも変わりません。
しかし、遺留分権利者がこの形成権を行使しただけでは、期限の定めのない債務となることから履行遅滞とはならず、具体的な金額を明示して請求したときに初めて履行遅滞となり、それ以後の遅延損害金が発生すると考えられます。
さらに、形成権の行使としての請求をした場合にも、一般の金銭債権となるのですから、ここから一般の債権の消滅時効にかかる可能性が出てくることに注意が必要です。
この消滅時効の期間については、請求が債権法の改正の施行後にされたものであれば、5年と考えられています。
厳密に考えると、相続法の改正後に相続が開始し、債権法の改正後に遺留分侵害額請求権が行使された場合には、消滅時効の期間が10年になるのか、5年になるのかについての議論がありえますが、後者になるという見方が有力です。
3 期限の許与の制度
⑴ ただちに金銭を支払うことが困難な場合の対応
このように、遺留分についての権利が金銭債権化されたわけですが、遺産の内容が不動産のみでほとんど預貯金などがなかった場合、不動産が栄等の地価の高い場所に所在していた場合には、遺留分の侵害額が多額になり、遺留分義務者が金銭をただちに支払うことが困難な場合がありえます。
このような場合への対応策として、立法段階では、義務者から給付を受けた現物を代替して給付することができる方法も検討されましたが、義務者に選択権を認めた場合には不要な不動産のみを権利者に押し付けることになるのは不合理であるし、仮に、この内容を裁判所の裁量的判断に委ねたとしても、その内容が当事者にとって予測できないのは妥当でないと考えられたことから、これらの案はいずれも採用されませんでした。
その代わりに、金銭債務の支払時期について、義務者からの請求があった場合には、裁判所がその金銭債権の全部または一部について、相当の期限を許与することができるというルールが導入されることになりました。
⑵ 期限の許与はどのような場合に認められるのか
明確なルールが示されていませんが、請求された遺留分侵害額請求の数額や贈与や遺贈の内容、請求がされた時期、許与が求められた時期などの諸般の事情が考慮され、裁判所の裁量によって判断されるものと考えられます。
この期限の許与が裁判所に認められた場合には、その認められた範囲について、その期限の許与が認められた日の翌日以降について、履行遅滞となって遅延損害金が生じると考えられています。
⑶ 期限の許与を認めてもらう方法
裁判所に期限の許与を認めてもらう方法については、遺留分権利者から訴訟提起がされていない場合には、権利者を被告として、期限の許与を求める形成の訴えを提起することができると考えられています。
では、遺留分権利者からすでに訴訟が提起された場合には、期限の許与を求める旨の意思表示を攻撃防御方法として提示するだけで足りるのか、別に上記の訴えを提起する必要があるのかについては、意見が分かれているようです。
場合によっては、遅延損害金の額が多額になったり、強制執行によるリスクが高かったりする場合がありますので、実務での取り扱いが固まらない場合には、その方法について慎重に判断する必要があるところです。